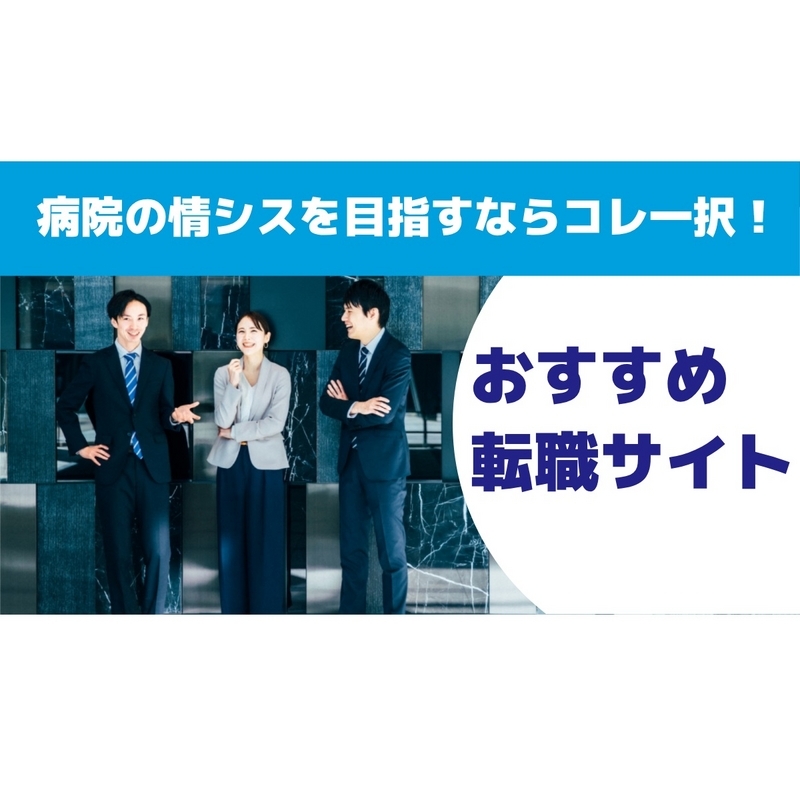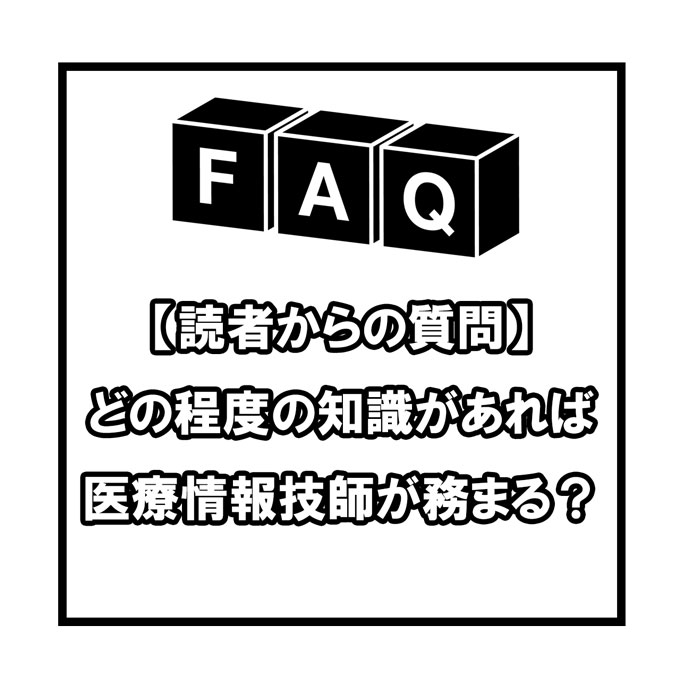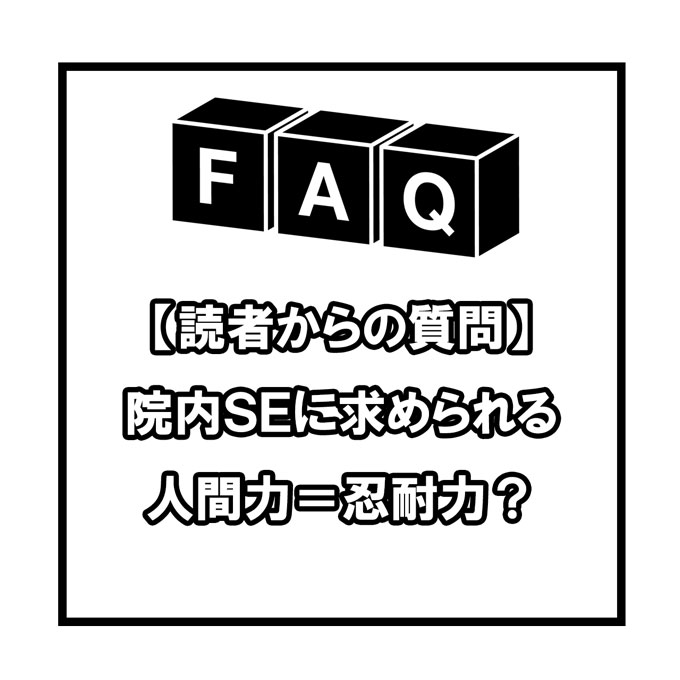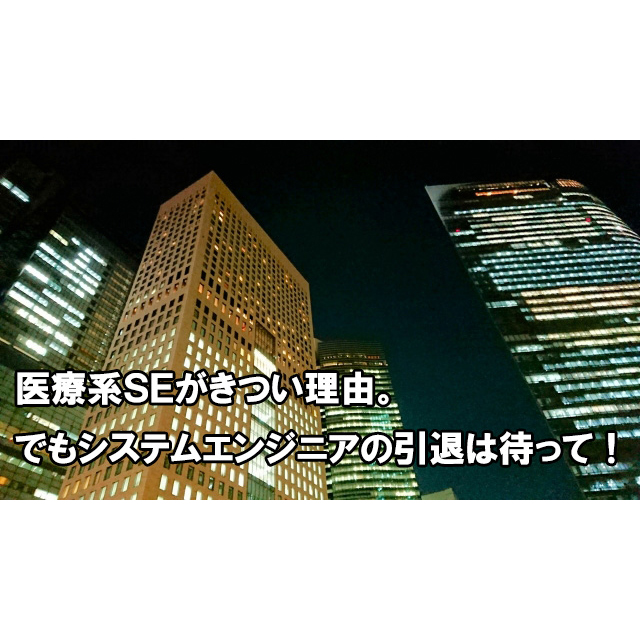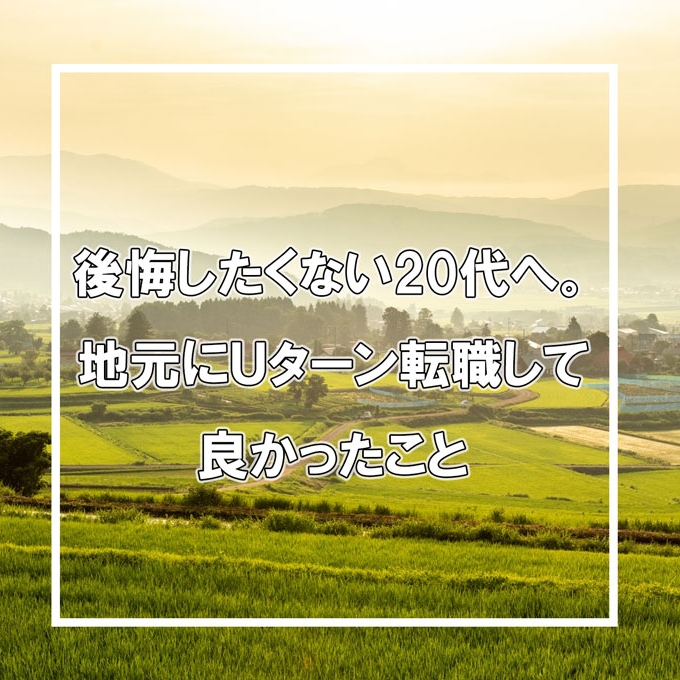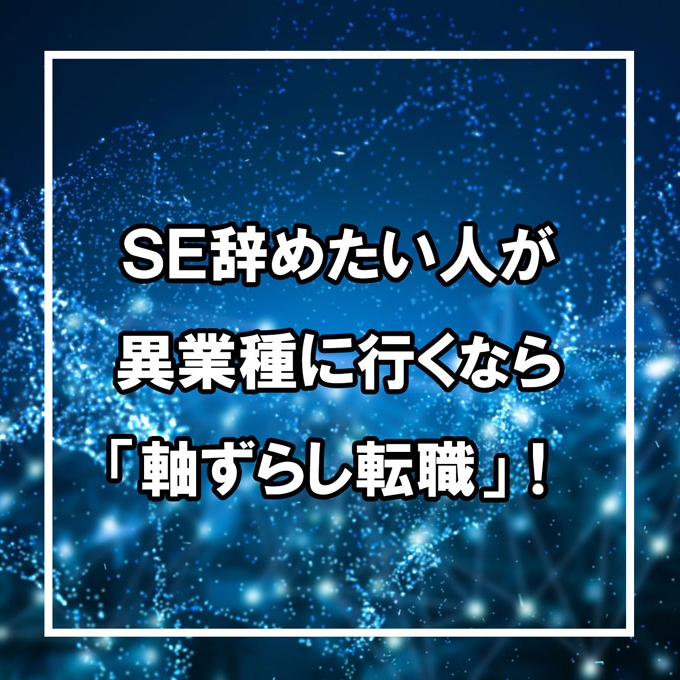病院のSEとして10年以上働いている白狐(しろぎつね)です。
長いことシステム管理をやっていると、さまざまなトラブルに遭遇します。大抵は些細なものですぐに対処できますが、時としてまったく想定外の事態が起こります。想定外なだけに、解決までに多くの手間と時間が掛かるもの。
いろんなトラブル事例を知っておくと、同じ現象に出くわしたときのヒントになります。一つでも多く知っておき、解決策の引き出しを多く持っておくに越したことはありません。
この記事ではひとり情シスとしてワンオペ業務を回す私が、過去に経験してキツかったトラブルを3つ共有したいと思います。
目次
応援してくださる方は、励みになりますので「人気ブログランキング」ボタンのクリックをお願いします!
※クリックすると私に票が入ります。押すだけなら無料(笑)!情報が取られる等はありませんので、ぜひ応援よろしくお願いしますm(_ _)m
システムエンジニアランキング
【3位】 床下のスパゲッティケーブル整理案件
院内SEがあまりやりたくない肉体労働の一つが、ケーブルの敷設作業です。オフィスのレイアウト変更や部署移動をするとき、LANケーブルを新たに敷いたり、配線の変更をしたりします。WiFiにすれば手っ取り早いのですが、回線速度を安定させたいときや、WiFiルータの設置場所に電源を確保できないときは有線LANを使います。
そういう仕事は業者に外注しないの?
ちょっとした作業だったら、わざわざ費用をかけて頼むことはしませんね・・・
LANケーブルを床の上に這わせるとつまずく危険があるので、可能な場合は床下に埋めるのですが、厄介なのが既存ケーブルの整理。前任者がいないと、どのケーブルがどこに繋がっているのか分からず、新たに線を敷くにもどこから引っ張ってくるのか悩みます。しかもコードがぐちゃぐちゃに絡まってスパゲッティ状になっていて、何がなんだかさっぱり分からない・・・そんな案件がありました。
▼LANケーブルのほか、電源コード、モジュラージャック、なにかよくわからないケーブルなんかも混ざってたりします。見るだけでうんざりです・・・。

しかも作業場所が床下なので、引っ張るだけではコードが絡まるばかり。ほぐそうにも、ケーブルを手繰り寄せたり、奥に追いやったりするのが一苦労。タイルを剥がしたり、ケーブルキャッチャーで引っ張ったりして悪戦苦闘しながら配線作業をしました。
▼ちなみに、ケーブルキャッチャーとはこういうツールです。先端にケーブルを引っ掛け、棒を伸縮させることで配線を行います。
今でこそ、回線の種類(インターネット回線か院内LANか)によってケーブルを色分けしたり、見出しタグをつけたりして誰が見ても分かるようにしていますが、インターネット黎明期に敷かれたものだとそんなキレイには纏まっていません。前任者がおらず引き継ぎも受けていないと、現状把握からスタートするわけです。
床下や壁の中に埋まっているケーブルの行き先を推測して、LANの両端をそれぞれパソコンに挿して通信できるか確認する・・・などという地味な作業をしていきます。面倒で、手間と時間のかかる、一回やったら二度とやりたくない作業です。
長時間かけて配線を終えたあと「やっぱり、サーバの位置をあっちにずらしたいんだけど」とか言われたときは、
先に言えや!!
とブチ切れました(笑)。
それ以来、ケーブルを敷設するときは事前に部屋の平面図を用意し、どこにサーバやクライアントを置くか意識合わせしてからやるようにしています。「配線上、サーバはここに置く必要があります」「普段サーバ本体に触らないなら、クライアントから遠い場所に置いても大丈夫ですよ」といった話もします。
「実際に机を置いてみないと想像つかないんだけど~」と言われたりもしますが、後からレイアウト変更するのは大変なので、
後から変更はナシですからね!
と念押しもしています。そうすれば、後から文句言われても「あのとき確認したよね?」と返せますので。
ケーブル配線って、天井裏や床下、壁の中に這わせることがよくあるので、それなりの肉体労働なんですよね。
▼院内SEの現場仕事に必要なアイテムを、こちらの記事で紹介しています。興味があれば、ぜひ併せてお読みください。
【2位】 院内LANのループ案件
「掃除のおばちゃんがハブにケーブルを指した」ことでループが起きるのはあるあるですが、コレ、実際に起きたことがあります。(掃除のおばちゃんなのか、職員の誰かなのかは定かではありませんが)
出勤してまもなく、「電子カルテが動かない」と外来から呼び出し。急行するとネットワークエラーとなって通信不能の状態であったものの、なぜか他のパソコンは正常に動作していました。端末固有の問題かと思いきや、他のフロアは正常だし、同じフロアでも一部のパソコンは問題なく稼働している。
ルータやハブの故障か?と疑っていたところ、正常なパソコンが次第にエラーになっていきました。
「時間差」でネットワークエラーになっていくことがヒントとなり、ループが起きているのではと推測。当時ハブにはループ検知機能が付いていなかったので、院内のルータ・ハブを片っ端から探し、ケーブルがループ接続になっていないか点検していきました。
▼こういう接続の仕方がループ。情シス泣かせの、あるあるトラブルの一つです。

しらみつぶしに探し回りましたよ。「誰だよ犯人は!!」と心で叫びながら。
ルータやハブといった中継機が故障した場合、配下にある端末は当然ネットワークエラーが発生します。なので、同じエリアにあるパソコンがネットワークエラーになっていれば中継機の故障を疑うことができますが、同エリアにあるパソコンでも部分的にエラーが出ている場合は、LANケーブルの断線・損耗など、限定された範囲の故障だと判断できます。
いっぽうループの場合、ネットワークエラーが徐々に波及していくので、時間差でエラーになることが多いのです。
どこでループになっているかなんて分かりませんので、手当たり次第にポートをチェックしました。これほど非生産的で、ただただ時間を消費する、無駄な仕事ってないですよね・・・。
これを受けて、再発防止として導入したのがLANポートのキャップ。空のポートを物理的に埋めることで、下手にケーブルが繋がれないよう手を打ちました。アナログなやり方ですが、それこそ掃除のおばちゃんにも伝わるので、意外と効果があっておすすめです。
余談ですが、ループをソフトウェアから検知する方法もあります。YAMAHAのルータでは、ネットワーク構成をGUIで可視化し、ループ発生箇所を検知できる機能があります。

LANマップでネットワーク全体を可視化 : Web GUI設定
https://network.yamaha.com/setting/router_firewall/monitor/dashboard/lan_map_rt
最近のハブはループ検知機能がありますのでハブ本体を見れば目視で分かることですが、ルータの管理画面から一元管理できるのは楽ですよね。LANの規模が大きい場合は、ぜひ使いたい機能ではないでしょうか。
▼YAMAHAのルータは耐熱性能も高く、40℃に達する真夏日でも安定稼働してくれるので業務用におすすめできます。こちらの記事でクローズアップしています!
【1位】 北海道胆振東部地震によるブラックアウト

北海道のブラックアウト、なぜ起きた? | 日経クロステック(xTECH)
https://xtech.nikkei.com/dm/atcl/feature/15/031400070/090700076/
1位は、全国にも衝撃が走ったであろう、2018年に起きた北海道全域ブラックアウト。2018年9月6日午前3時7分、北海道の胆振東部を震源地とする地震が発生し、これにより北海道全域が停電するという未曾有の事態が起きました。私が住む地域は地震の直接的な被害はありませんでしたが、停電により院内のさまざまな電気機器が影響を受けました。
北海道ってこれだけ広いのに、全域停電なんて信じられなかったですよ。
東京~大阪までの一帯が停電したようなものか・・・
【道民は思った】
— じわじわ笑えるシュールネタ (@jiwajiwaneta) 2013年8月19日
他県民「2泊3日で北海道旅行行きたい ♥」
他県民「まずは札幌行って観光してから小樽行く♥」
他県民「それから旭川行って富良野の行って ♥」
他県民「帰りは函館見て帰りたい ♥」
ほぼ移動 pic.twitter.com/QmlZl8yRpC
院内サーバは非常電源に繋がっていたため落ちることはなかったものの、電源の供給は生命に関わる医療機器が優先。いつまで非常電源が持つのか、サーバをいつ、どんな手順でシャットダウンさせるか、といった決断が迫られました。
幸いにも地震発生日の夜には電力が復旧したため、結果的にサーバは落とすことなく稼働を続けられたのですが、日中はずっとサーバに張り付き、電子カルテシステムを最小構成で動かすにはどうするか、落としてもいいシステムはどれか、などを思案していましたね。
基本的に、落としても問題ない部門システムはありません。必要だから常時稼働させているわけであり、落としてよいとすれば、それはそもそも常時稼働する必要ないよね?ということになってしまいます。なので、どの部署も「うちのシステムは落とされたら困る!」と言ってきます。そんな中でも優先順位をつけ、やむを得ず落とす場合はその代替手段を提案し、受け入れてもらうしかありません。
システムをフル稼働させられない場合は、端末構成を最小限に絞り、カルテの参照やプリンタなど最低限なくてはならないものだけを動かすようにします。
他の病院では、サーバが非常電源に繋がっていなかったため落ちてしまい、外来診療を中止したり、入院患者の受け入れを停止したりしていたところもあったようです。このときほど、BCP対策の大切さを痛感させられたことはないですね。
こうした経験があると、ランサムウェアにしろ自然災害にしろシステムが突然停止する事態はいつでも起こり得ることで、明日は我が身、ということを思い知らされます。
電力が復旧するまでの間、夜は信号機も街灯も消えていたので、不気味なうえ外での行動は危険でしたが、みな譲り合いの精神で車の運転もゆっくりしており、大きな混乱が起きなかったのが救いでした。
▼ブラックアウト時の札幌・すすきのの様子。車のヘッドライトやテールランプ以外の灯りがなく、本当に不気味な夜でしたね・・・。

北海道地震:ブラックアウト 負荷遮断、設定量検証へ 来月中間報告 | 毎日新聞
▼北海道は本当に広いです。札幌は観光地としても人気ですが、工夫すれば他のエリアにもついでに寄ることができます。北海道民の私が、おすすめの「ついで寄り」方法をこちらの記事で紹介していますので、ぜひ併せて読んでみてくださいね。
以上、院内SEとして10年以上働く私が経験した、二度とやりたくないトラブル3選を紹介しました。
情シスにとってキツいトラブルというのは、「終わりが見えない」「非生産的で不毛」なものではないでしょうか。1位に挙げたブラックアウトは、不確定要素が多い中で各部署と折り合いをつけながら優先順位を考えて対処するという、知識も経験も求められる最高レベルの難易度でしたが、学びも得られた事案でした。
いっぽうハブのループに関しては、そもそもループが原因かどうかも断定できないなかで、「おそらくループしているはず」という推測のみで作業を進めなければならず、もし見つからなかったら探した時間が無駄に終わる・・・というストレス極まりない案件でした。
二度とひどい目に遭わないよう、トラブルのあとはしっかり再発防止策を立てておきたいですね。
最後に
当ブログでは、病院に勤務するシステムエンジニアの私が、関係法令の改正やパソコンのトラブルシューティングなどをSE目線から紹介しています。
面白いと思ったら、ぜひブラウザにお気に入りの登録をお願いします!
人気記事もぜひ読んでいってくださいね。
▼面白かったと思って頂けたら、ぜひ下の「人気ブログランキング」のボタンを押してください!